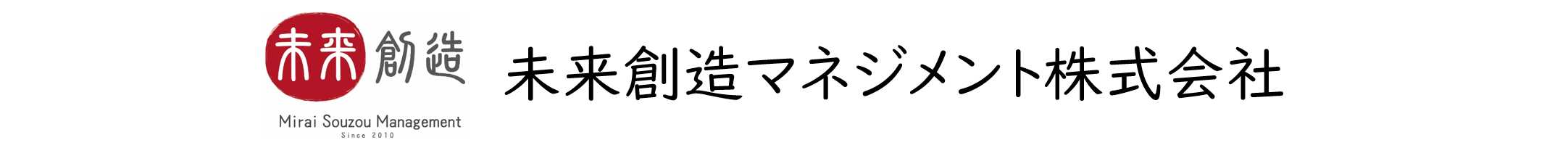基本毎週日曜日にブログ更新を心がけているけれども、先週どうしても更新するスキマ時間が作れなくて、ちょっとだけへこんでしまった未来創造マネジメント・umayado townの谷口です。
昨年12月15日に、弊社が地域活性事業に取り組んでいる理由についてブログを書きましたが、一つ書き忘れていることがあることに気がつきました。それは地域活性事業が「私の強みを活かすことができる事業である」と判断したからです。
経営を考えるときに強みはとても大事ですので改めてそんな話しを。

地域活性事業をやる理由としての強み。
未来創造マネジメントが税理士・コンサルの傍ら、京丹後市の間人で地域活性事業を行っている理由として、その強みが生きるから、ということなのですが、それはどんな強みであるかというと、
・不動産関係の知識が豊富
・投資収益回収の計算が得意
・人の輪を広げていくのが得意
ということです。
それぞれ説明しているとえらい長文ブログになる予感がするので、それについてはまた機会があれば。
ただ兎にも角にも、新たな事業領域に踏み出そうとするとき、それは「飛び石」であってはいけません。ちゃんと何某かの根っこがつながっている必要があります。
その根っこの一つが何かというと、自社の強みを活かすことができるか、ということです。
ビジネスシナリオの話しをするときに、このブログでも何度も書いてますが、事業領域を設定する際には
「求められること」「したいこと」「できること」
この3つを満たしている必要があります。
そしてその中で「できること」というのは、会社内部に備えている強力なリソースのことです。
これを正しく活用してこそ、新たな事業はうまく育っていくことができます。
ここでいうところの「できること」というのは別の言葉に置き換えるならばそれが、「強み」ということなんです。
つまり「強み」が活きない事業、それは『手を出してはいけない事業(領域)』であるということになります。当然と言えばとうぜんですよね。
強みでしか生きていけない!
事業はどんなものであっても極論、常に他社との競争にさらされ続けています。
強烈な競争にさらされている以上その世界で顧客から選ばれ続けるためには、独自性が必要ですし、少なくとも他社と同じ土俵で戦っている場合ではありません。
ですから事業は「強み」の世界でしか生き抜くことはできません。
逆に強みでない部分でどれほど頑張っても成果はでないし、しんどいし、何一ついいことはありません。
幸い今の時代、この地球上の距離はどんどん縮んでいます。情報なんて距離ゼロですし、モノを購入するときにもネットで買えば地球の裏側から届きますし、zoomなどのリモートの発達によってサービスも普通に遠隔提供できるものが増えました。
したがって今の時代(というかずっと前から)、地域一番であることよりも「グローバルニッチ」であることが重要になっています。
特に小零細企業は大企業と同じ土俵で勝負はできませんから、大企業の入り込めないニッチな世界で柔軟に事業展開していくことが絶対的に求められます。
また買い手側を見ても、市場はどんどんと際限なく細分化されて、個人の中で「こだわらない買い物」と「徹底してこだわりたい買い物」の二極化がさらに先鋭化しています。
だからこそ「強み」を徹底的に追求することが求められますし、そこでしか生き残っていけないのです。
小零細企業は(大企業もですが)、「自社の強みは何か」ということを永遠に問い続けル必要があるんです。
「強みは何か」という危険な問い。
最近読んだ本「人生の経営戦略」(山口周 著)で、『「強みは何か」というのは危険な問いである』というような一節がありました。
なぜなら人は自分の強みがわからないから。
人間というのは、自分自身の能力を過信したりまたは卑下したりして自己評価を見誤るに十分なほどにポンコツである、ということです。
これ自体に対しては激しく同意します。人間どこまで行っても自己を客観視することはできません。
ではそれに対して山口氏がどのような回答を記しているかというと、「楽しめること」「長く続けられること」「どれだけ長く親しんできたものであるか、ということ」が大切であると説いています。
つまり「強みで勝負する」ということを山口氏は否定しているわけではなく、むしろそれ自体は強く肯定しています。ただ「強みは何か」という問いかけ自体が危ない、と。
なぜならその問いかけでは自身の強みにたどり着けないので。
その替わりに「自分の楽しめるものは何か」「長く続けられることは何か」「長く親しんできているものは何か」という問いかけをするべきだとおっしゃってるわけです。
強みで勝負する以上、それ自体を見誤ってしまっては正しい経営戦略は描けません。
いかに正確に自己の「強み」にたどり着くか。それに対する答えが上記の問いかけであり、あとは「人に聞く」「人から教えてもらう」ということだろうと思います。
他人からの視点はは客観ですから。
場合によっては顧客に尋ねるのもいいでしょう。
ただそれも、その全てが正解であるとは限りません。むしろ間違いの方が多いだろうと思います。
なぜなら他人は客観ではありつつもそれほど自分のことを知っているとも限らないからです。また他人は当然無責任な立場だからです。
ですから「全てが正解」ということではなく、「そのなかに正解があるかも」というくらいが正しいですね。
「自分の中に正解はないから、正解がある可能性がある場所にそれを求める」という感じです。
そしてもう一つの強みの見つけ方は、「ファクト(事実)から導き出す」です。
これまでそれなりに一生懸命仕事をされてきた方、それなりに真剣に人生を生きてこられたかたは、良くも悪くもこれまで多くの結果を生み出してきているでしょう。
その中で良い結果を生み出しているその原因として共通してあがってくるものは「強み」として考えていいんじゃないかと思います。特に事業において良い結果につながっているものは。
自分がどう考えてようと事実は事実ですから、この分析結果はわりと信用できるものじゃないかな、と思います。
ただ入り口の段階で良い結果でもなんでもないものを「良い結果」として考えちゃダメですよ。
まぁそこまで甘甘な人は経営者に向いてないのかもしれませんが。